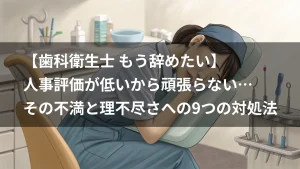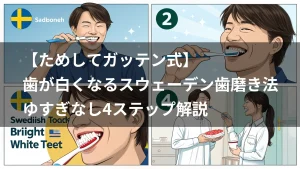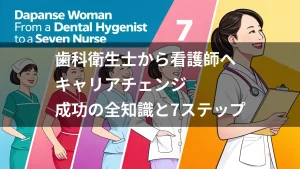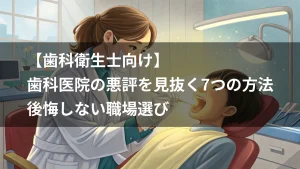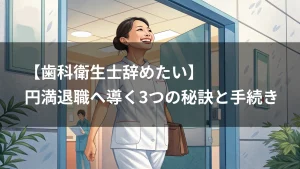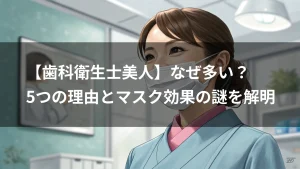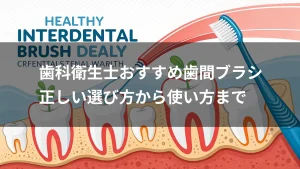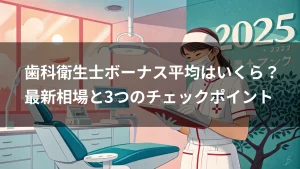歯科衛生士の業務範囲、特にレントゲンへの関与については、正確な知識が不可欠です。
特に、レントゲン撮影の照射スイッチを押す行為は法律で明確に禁止されており、この点を理解しておく必要があります。
この記事では、歯科衛生士によるレントゲン撮影がなぜ違法なのか、その法的根拠と罰則、歯科衛生士が行える準備や介助などの業務範囲、そしてスキルアップに繋がるレントゲン読影の重要性について、分かりやすく解説します。
 mimi
mimiえっ、ボタンを押すのはダメなんですね…どこまでなら大丈夫なんですか?



はい、法律で業務範囲が決められています。この記事で詳しく確認しましょう。
- 歯科衛生士によるレントゲン撮影(照射)の違法性とその法的根拠
- 違反した場合の罰則(歯科衛生士本人と指示した歯科医師)
- 歯科衛生士が行えるレントゲン関連業務の具体的な範囲
- レントゲン写真の読影スキルを習得するメリット
歯科衛生士のレントゲン業務、どこまでOK?


歯科衛生士の業務範囲でレントゲン撮影にどこまで関与できるかは、非常に重要なポイントです。
結論として、照射スイッチを押す行為は法律で禁止されていますが、準備、介助、読影は歯科衛生士の重要な役割です。
法律で定められた範囲を正しく理解し、適切な業務を行うことが求められます。
レントゲン撮影ボタンを押すのは違法行為
歯科医療現場で日常的に行われるレントゲン撮影において、歯科衛生士が照射スイッチを押す行為は、法律で明確に禁止された違法行為です。
たとえ院長や歯科医師からの指示があったとしても、「他の医院もやっているから」という理由があっても、この行為は許されません。



えっ、ボタンを押すのはダメなんですか?



そうなんです。法律で厳しく定められています。
自身の身を守るためにも、このルールは必ず守る必要があります。
法律で定められた撮影可能な職種
人体に放射線を照射するレントゲン撮影は、誰もが行えるわけではありません。
診療放射線技師法により、レントゲン撮影を行えるのは医師、歯科医師、そして医師または歯科医師の指示を受けた診療放射線技師のみと厳密に定められています。
| 撮影可能な職種 | 根拠法 |
|---|---|
| 医師 | 診療放射線技師法 |
| 歯科医師 | 診療放射線技師法 |
| 診療放射線技師(医師等の指示下) | 診療放射線技師法 |
この法律は、患者さんの安全を守るために非常に重要な役割を果たしています。
なぜ歯科衛生士は撮影できないのか
歯科衛生士がレントゲン撮影を行えない理由は、診療放射線技師法に資格が規定されていないためです。
レントゲン撮影は人体に放射線を照射する医療行為であり、専門知識、技術、被ばく管理が不可欠です。
そのため、法律で定められた資格を持つ者だけが行えるように制限されているのです。



なるほど、資格が必要な専門的な行為なんですね。



その通りです。安全に行うために法律で決まっているんですよ。
歯科衛生士は口腔ケアの専門家ですが、放射線照射に関する資格は持っていないため、撮影行為はできません。
準備や介助は歯科衛生士の仕事
照射スイッチを押すことはできませんが、撮影の準備や患者さんの介助は、歯科衛生士の重要な業務範囲です。
具体的には、レントゲン装置の準備・調整、患者さんへの説明・誘導、フィルム装着の補助(ポジショニング補助)などが含まれます。
これらは歯科医師の指示のもとで行うことができます。
| 歯科衛生士ができるレントゲン関連業務 |
|---|
| 撮影装置の準備・調整 |
| 患者さんへの説明・誘導 |
| フィルム装着・位置調整の補助 |
| 撮影後の現像・データ管理 |
これらの補助業務を通じて、円滑で安全なレントゲン撮影をサポートする役割を担っています。
レントゲン写真の読影は推奨されるスキル
撮影はできませんが、レントゲン写真(X線写真)を読み解く「読影」スキルは、歯科衛生士にとって習得が推奨される価値ある能力です。
読影スキルを習得すれば、むし歯の進行度や歯周病による骨吸収の状態などを把握でき、患者説明がより分かりやすく、歯科医師との連携もスムーズになります。



読影ができると、仕事の幅が広がりそうですね!



ええ、スキルアップにも繋がりますし、患者さんへの貢献度も高まりますよ。
読影能力を高めることは、歯科衛生士自身の専門性を高め、日々の臨床に大きく貢献します。
レントゲン撮影に関する法律と罰則


歯科衛生士がレントゲン業務に関わる上で、関連法規の理解は不可欠です。
特に、レントゲン撮影の根拠法である「診療放射線技師法」の内容を把握することが重要です。
この法律では、誰が放射線を照射できるのか、違反した場合の具体的な罰則内容、そして、たとえ指示があったとしても歯科衛生士本人や指示した歯科医師がどのような責任を問われるのか、さらには過去の摘発事例から学ぶべきリスクについて定められています。
この法律を正しく理解・遵守することが、歯科衛生士自身と勤務先の歯科医院を守る上で非常に重要です。
根拠となる診療放射線技師法
レントゲン撮影の法的根拠となるのは「診療放射線技師法」という法律です。
この法律は、放射線診療の安全確保と国民の健康保護を目的として制定されました。
診療放射線技師法第24条は、「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、放射線を人体に対して照射してはならない」と明確に規定しています。
つまり、歯科衛生士がレントゲン装置の照射スイッチを押す行為は、この法律に違反します。



歯科衛生士は放射線技師ではないから、撮影はできないってことですよね?



はい、その通りです。歯科衛生士はこの規定に含まれていないため、レントゲン撮影の照射ボタンを押すことはできません。
歯科衛生士はこの法律を理解し、自身の業務範囲を正しく認識する必要があります。
法律で定められた役割の遵守が、安全な医療提供につながります。
違反した場合の具体的な罰則内容
診療放射線技師法に違反し、無資格者がレントゲン撮影を行った場合の罰則は、法律で具体的に定められています。
これは患者さんの安全を守るための重要な規定です。
同法第31条によれば、無資格で放射線照射を行った者には「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
これは決して軽い罰則ではなく、違反行為の重大性を示しています。
「知らなかった」「他の人もやっている」「指示されたから」といった理由は通用しません。
法律違反のリスクを十分に理解し、常に法令遵守の意識を持つことが求められます。
歯科衛生士本人への罰則
違法なレントゲン撮影を行った場合、照射スイッチを押した歯科衛生士本人も処罰対象となります。
これは「知らなかった」では済まされない、重大な問題です。
前述の通り、診療放射線技師法第31条に基づき、歯科衛生士がレントゲン撮影を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
| 罰則対象 | 根拠法条 | 罰則内容 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士本人 | 診療放射線技師法第31条 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(併科あり) |
この罰則は、歯科衛生士としての資格やキャリアにも重大な影響を及ぼす可能性があります。
自身の将来を守るためにも、法律で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
指示した歯科医師への罰則
違法なレントゲン撮影は、実行した歯科衛生士だけでなく、それを指示した歯科医師にも責任が問われます。
歯科医院全体のコンプライアンス意識が重要です。
歯科衛生士にレントゲン撮影を指示した歯科医師も、診療放射線技師法違反の共犯として、または使用者としての管理責任を問われ、歯科衛生士本人と同様の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があります。
| 罰則対象 | 根拠法条 | 罰則内容 |
|---|---|---|
| 指示した歯科医師 | 診療放射線技師法第31条(共犯等) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(併科あり) |
歯科医師からの指示であっても、違法な指示には従えません。
疑問に感じた場合は、勇気を持って確認し、法令遵守を優先する姿勢が大切です。
過去の摘発事例から学ぶリスク
過去には、歯科衛生士や歯科助手によるレントゲン撮影の摘発事例が存在します。
これは決して他人事ではありません。
例えば2019年1月、大阪府で診療放射線技師法違反の疑いで歯科医師や歯科助手(報道内容から歯科衛生士を含む可能性あり)計11名が書類送検されました。
さらに同年10月には名古屋市で、同様の違反に加え、無資格者が行った医療行為について診療報酬を不正請求したとして、詐欺罪(10年以下の懲役)の疑いで歯科衛生士が立件されたケースもあります。



実際に逮捕されたりしてるんですね…知らなかったです。



そうなんです。「他の医院でもやっているから大丈夫」といった安易な考えは非常に危険です。法律違反のリスクをしっかり認識することが大切ですよ。
これらの事例は、法律軽視や安易な考えによる違法行為の危険性を示しています。
自分自身と患者さん、そして歯科医院を守るためにも、法律遵守の重要性を常に意識しましょう。
歯科衛生士ができるレントゲン関連業務の範囲


レントゲン撮影のボタンを押す行為は法律で禁止されていますが、心配しないでくださいね。
レントゲン撮影に関連する業務の多くは、歯科衛生士が法的にも行うことができる大切な仕事です。
具体的には、撮影装置の準備や調整から、患者さんへの説明と誘導、フィルムの装着や位置調整の補助、撮影後の現像やデータ管理まで、多岐にわたります。
また、これらの業務範囲を正しく理解するために、絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の違いを知っておくことも重要です。
法律で定められた範囲を理解し、自信を持って日々の業務に取り組めるよう、一つひとつ確認していきましょう。
撮影装置の準備や調整
レントゲン撮影を行う前の装置の準備や調整は、歯科衛生士が行える業務の一つです。
スムーズで安全な撮影のためには、装置の電源投入、撮影部位や目的に合わせた照射条件(電圧、電流、照射時間など)の入力・確認、必要に応じて撮影モードの選択など、事前のセッティングが非常に重要になります。
歯科医師の指示に基づき、これらの準備を正確に行うことが求められます。
| 準備・調整の例 | 内容 |
|---|---|
| 電源投入 | レントゲン装置本体や関連機器の電源を入れる |
| 照射条件設定 | 撮影部位や目的に合わせ、電圧・電流・時間を設定 |
| 撮影モード選択 | デンタル、パノラマ、セファロなどのモードを選択 |
| 器具の準備 | フィルムホルダーやバイトブロックなどを準備 |
| 装置の位置調整(予備) | 患者さんを導入する前に大まかな位置を調整 |



準備もどこまでやっていいのか不安でした…



照射ボタンを押さない限り、機械のセッティングは大丈夫ですよ
これらの準備作業は、歯科衛生士の大切な業務範囲です。
装置の操作方法をしっかりと習得し、安全管理に注意しながら、撮影が円滑に進むようサポートしましょう。
患者さんへの説明と誘導
レントゲン撮影前の患者さんへの丁寧な説明や、撮影室へのスムーズな誘導も、歯科衛生士の大切な役割です。
多くの患者さんは、レントゲン撮影に対して「被ばくは大丈夫かな?」「何のために撮るのかな?」といった不安を感じています。
そのため、撮影の目的や大まかな流れ、時間はどのくらいかかるのか、そして被ばく線量は健康に影響がないレベルであることなどを分かりやすく説明することで、患者さんの不安を和らげ、安心して検査を受けてもらうことができます。
また、撮影室へ案内し、防護エプロンの着用をお願いするなど、具体的な誘導も行います。



患者さんに質問されたときに、どこまで答えて良いか迷うことがあります



撮影の必要性や手順を丁寧に説明して、安心させてあげてくださいね
患者さんとのコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、リラックスした状態で撮影に臨んでもらうことが、より正確な診断に必要な質の高いレントゲン写真を得るための第一歩となります。
フィルムの装着や位置調整の補助
デンタルレントゲンやパノラマレントゲン撮影時における、フィルムやセンサーの装着、正しい位置への調整補助(ポジショニングの補助)も、歯科衛生士が行うことのできる業務です。
特にデンタルレントゲン撮影では、患者さんの口の中にフィルムやセンサーを正しい位置に挿入し、しっかりと保持してもらうように指示する必要があります。
パノラマレントゲン撮影では、患者さんが正しい位置に立ち、顎を乗せ、バイトブロックを軽く噛んでもらうよう誘導します。
これらの補助は、撮影する部位を正確に画像に収めるために非常に重要です。
| 補助行為の例 | 具体的な内容 |
|---|---|
| デンタルフィルム/センサー装着 | 口腔内の撮影部位に正確に挿入・保持を指示 |
| フィルムホルダーの使用補助 | ホルダーの適切な位置づけをサポート |
| パノラマ撮影時の位置誘導 | 正しい立ち位置、顎の位置、バイトブロックの噛み方を指示 |
| セファロ撮影時の位置誘導 | 頭部固定器具への正しい位置づけをサポート |
| 防護エプロンの装着 | 患者さんへの防護エプロン着脱のサポート |



ポジショニングって、意外と難しいんですよね…



正確な画像のためには、この補助がとても大切なんですよ
不鮮明な画像を避けるためには、患者さんにできるだけ動かないようにお願いすることも含め、適切なポジショニングの補助が不可欠です。
歯科医師の指示のもと、丁寧な補助を心がけましょう。
撮影後の現像やデータ管理
撮影が終わった後のフィルムの現像作業(従来のアナログレントゲンの場合)や、デジタルレントゲン画像のデータ管理も、歯科衛生士の業務範囲です。
アナログレントゲンの場合は、現像液や定着液の管理、適切な手順での現像・定着・水洗・乾燥作業が求められます。
近年主流のデジタルレントゲンの場合は、撮影された画像をコンピューターに取り込み、患者情報と紐づけて保存・管理する作業が中心です。
画像の明るさやコントラストの調整といった基本的な画像処理操作や、データのバックアップなども重要な業務に含まれます。



最近デジタルになったけど、操作にまだ慣れなくて…



画像の管理も大切な業務です。わからないことは確認しながら進めましょう
撮影された貴重な患者情報を適切に管理し、いつでも参照できるように整理しておくことは、正確な診断と治療計画の立案に不可欠です。
定められた手順に従い、責任を持って管理しましょう。
絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の違い
歯科衛生士の業務範囲を理解する上で、「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の違いを知っておくことが重要です。
絶対的歯科医行為とは、歯科医師免許を持つ者でなければ行うことができない医療行為を指します。
これには、診断、治療計画の立案、外科手術、そしてレントゲン撮影(X線照射)などが含まれます。
一方、相対的歯科医行為とは、歯科医師の直接の指示や監督のもとであれば、歯科衛生士も行うことができる医療行為です。
これには、歯石除去(スケーリング)、歯面研磨、フッ化物塗布、ブラッシング指導、そしてレントゲン撮影の準備や補助などが該当します。
| 行為の種類 | 具体例 | 実施者 |
|---|---|---|
| 絶対的歯科医行為 | 診断、治療計画立案、抜歯、歯を削る処置、レントゲン撮影(照射) | 歯科医師のみ |
| 相対的歯科医行為 | 歯石除去、歯面研磨、フッ化物塗布、ブラッシング指導、レントゲン準備・補助 | 歯科医師の指示・監督下で歯科衛生士も可能 |



どこまでが自分の仕事なのか、線引きが難しいと感じていました



レントゲン照射は絶対的歯科医行為。しっかり区別して業務にあたりましょう
レントゲンの照射ボタンを押す行為は、絶対的歯科医行為にあたるため、歯科衛生士が行うことはできません。
この区別をしっかりと理解し、自身の業務が法律で認められた範囲内であることを常に意識することが、安全で適法な医療を提供するために不可欠です。
歯科衛生士のスキルアップに繋がるレントゲン読影の重要性


歯科衛生士にとって、レントゲン写真を読み解く「読影」スキルは、日々の業務の質を高め、専門性を深める上で非常に重要です。
撮影自体は法律で禁止されていますが、読影能力を身につけることで、診療効率の向上、患者さんへの分かりやすい説明力アップ、歯科医師との連携強化、患者満足度の向上、そして自身の専門性と自信の向上に繋がります。
読影スキルは、これからの歯科衛生士に求められる大切な能力と言えるでしょう。
読影スキルがもたらす診療効率の向上
「読影」とは、レントゲン写真に写し出された情報を正確に読み取り、口腔内の状態を把握することを指します。
このスキルがあると、例えば歯科医師が診療を始める前に、あなたが事前にレントゲン写真を確認し、むし歯や歯周病の進行具合、歯石の付着状況などを把握しておくことができます。
これにより、歯科医師への情報伝達がスムーズになり、診断や治療計画立案にかかる時間を約10%〜15%程度短縮することも期待できます。
結果として、医院全体の診療が効率的に進むようになります。



事前にレントゲンを見ておくことで、そんなに変わるものですか?



はい、少しの時間でも事前に情報を把握しておくことで、その後の動きが格段にスムーズになりますよ
読影スキルは、日々の忙しい業務を円滑に進め、より多くの患者さんに対応するための時間を生み出すことに貢献します。
患者さんへの分かりやすい説明力アップ
読影スキルは、患者さんへの説明においても大きな力を発揮します。
レントゲン写真は、言葉だけでは伝えきれない口腔内の状況を視覚的に示すことができる有効なツールです。
あなたが読影スキルを持っていれば、「この黒い影がむし歯です」「歯を支えている骨がここまで下がっていますね」といったように、レントゲン写真の具体的な箇所を指しながら、患者さん自身の目で見て理解できるように説明できます。
例えば、歯周病の進行度を示す骨吸収の状態を、実際のレントゲン写真上のレベルで示すことで、患者さんは治療の必要性をより深く納得しやすくなります。
患者さんの不安を取り除き、治療へのモチベーションを高める上で、分かりやすい説明は欠かせません。
歯科医師との連携強化によるチーム医療への貢献
読影スキルは、歯科医師や他のスタッフとの円滑なコミュニケーションを促進し、チーム医療の質を高めるためにも重要です。
あなたがレントゲン写真から得た情報を的確に歯科医師に伝えることができれば、より迅速で正確な診断に繋がります。
例えば、「〇番の歯の根の先に透過像が見られます」といった具体的な所見を報告することで、歯科医師は問題点を素早く把握し、適切な対応を検討できます。
| 連携強化によるメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 情報共有の迅速化 | 診断や治療方針決定の迅速化 |
| 認識の齟齬防止 | より安全で確実な治療の実施 |
| 相互理解の深化 | スタッフ間の信頼関係向上 |
読影スキルを持つことで、あなたは単なるアシスタントではなく、診断プロセスにも貢献できるチームの重要な一員となることができます。
患者満足度の向上への寄与
歯科衛生士による分かりやすい説明や、スムーズな診療連携は、患者さんの満足度に直接的に繋がります。
読影スキルを活かして、患者さんが自身の口腔状態や治療内容をしっかりと理解し、納得して治療を受けられるようサポートすることは非常に大切です。
レントゲン写真を用いて「なぜこの治療が必要なのか」「治療によってどのように改善するのか」を具体的に示すことで、患者さんは安心して治療に臨むことができます。
丁寧な説明と質の高い医療提供は、歯科医院への信頼感を高め、「またこの医院で診てもらいたい」という気持ちに繋がります。
患者さんに寄り添い、満足度の高い医療を提供するために、読影スキルは欠かせない要素と言えるでしょう。
歯科衛生士としての専門性と自信の向上
読影スキルを習得することは、歯科衛生士としての専門知識を深め、日々の業務に対する自信を持つための大きな一歩となります。
レントゲン写真から多くの情報を読み取れるようになると、歯や歯周組織の状態をより深く理解できるようになり、予防処置や保健指導にもその知識を活かすことができます。
自分の判断や説明に根拠を持てるようになることで、仕事へのやりがいやモチベーションも高まるでしょう。



読影って難しそうだけど、私にもできるかな?



最初は難しく感じるかもしれませんが、学ぶことで確実にスキルアップし、自信につながりますよ
読影スキルは、あなたの歯科衛生士としての価値を高め、より主体的に、そして自信を持って働くための力となります。
読影スキルを学ぶ方法
読影スキルを身につけるためには、積極的に学ぶ姿勢が大切です。
幸い、現在では様々な学習方法があります。
| 学習方法 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 書籍 | 自分のペースで基礎から体系的に学べる | 石薬出版社の「歯科衛生士のための X線写真読本」など |
| セミナー・研修会 | 実践的な読影ポイントや症例を学べる、講師に直接質問できる | 各歯科衛生士会や歯科関連企業が主催するもの |
| eラーニング | 時間や場所を選ばずに動画などで学べる、繰り返し学習可能 | ORTC オンライン研修などのオンライン学習プラットフォーム |
| 院内での学習 | 勤務先の歯科医師に質問したり、症例検討会に参加したりする | 日々の臨床と結びつけて実践的に学べる |
まずは、自分が取り組みやすい方法から始めてみましょう。
例えば、基本的な読影のポイントが解説されている入門書を1冊読んでみる、興味のある分野のオンラインセミナーに参加してみるなど、小さな一歩からで構いません。
継続的に学習することで、着実に読影スキルは向上します。
ぜひ、自分に合った方法でスキルアップを目指してください。
よくある質問(FAQ)
院長からレントゲン撮影(照射ボタンを押すこと)を指示された場合、どう対応すれば良いですか?
歯科衛生士がレントゲン撮影の照射ボタンを押すことは法律で禁止されています。
まずは、法律(診療放射線技師法)で定められているため、照射ボタンを押す業務は行えないことを丁寧に説明しましょう。
その上で、撮影準備や患者さんの誘導、位置付けの補助など、歯科衛生士として行える範囲で最大限協力する姿勢を示すことが大切です。
どうしても理解を得られない場合は、他のスタッフや地域の歯科衛生士会などに相談することも考えてみてください。
歯科衛生士が行えるレントゲン撮影の「補助」には、具体的にどのような行為が含まれますか?
歯科衛生士が行えるレントゲン撮影の補助業務は多岐にわたります。
例えば、レントゲン装置の電源を入れたり、撮影条件を設定したりする「撮影準備」。
患者さんに撮影の目的や流れを説明し、不安を取り除きながらレントゲン室へ誘導する「患者誘導」。
そして、デンタルレントゲン撮影時にフィルムやセンサーを適切な位置に保持するよう指示したり、パノラマレントゲン撮影時に正しい立ち位置や顎の位置を案内したりする「位置付けの補助(ポジショニング補助)」などが含まれます。
撮影後の現像やデジタル画像の管理も業務範囲です。
もし違法と知りながらレントゲン撮影のボタンを押してしまった場合、指示した歯科医師だけでなく、私自身も罰せられるのでしょうか?
はい、その通りです。
診療放射線技師法では、無資格で放射線を人体に照射することを禁止しており、違反した場合の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、あるいはその両方)が定められています。
この罰則は、実際に照射ボタンを押した歯科衛生士本人にも適用されます。
たとえ歯科医師からの指示があったとしても、法律違反の責任を問われる可能性があることを理解しておく必要があります。
歯科助手さんも、歯科衛生士と同じようにレントゲン撮影の補助はできますか?
レントゲン撮影に関する業務範囲は、資格によって異なります。
歯科衛生士は国家資格であり、歯科医師の指示のもとでレントゲン撮影の準備や患者さんの介助、位置付けの補助といった行為が認められています。
一方、歯科助手は資格による業務独占がないため、原則として患者さんの口腔内に手を入れる医療行為(フィルムの装着補助など)はできません。
患者さんの誘導や簡単な準備など、間接的なサポートにとどまるのが一般的です。
レントゲン写真を読影できると、患者さんへの説明以外にどのようなメリットがありますか?
レントゲン写真を読影するスキルは、患者さんへの説明力向上だけでなく、多方面で役立ちます。
例えば、歯科医師が診察する前にレントゲン写真を確認し、気付いた点などを的確に伝えることで、よりスムーズな診断と治療につながり、チーム医療への貢献度が高まります。
また、歯周病の進行度などを自分で把握できるため、スケーリングなどの処置計画をより適切に立案しやすくなるでしょう。
結果として、自身の専門性が高まり、仕事への自信にもつながります。
最近はデジタルレントゲンが多いですが、従来のアナログレントゲンと比べて歯科衛生士の業務に違いはありますか?
基本的な業務範囲(撮影ボタンを押さない、準備や補助を行う)は、デジタルレントゲンでもアナログレントゲンでも変わりません。
ただし、撮影後のプロセスが異なります。
アナログの場合はフィルムの現像・定着・水洗・乾燥といった一連の作業が必要でしたが、デジタルの場合は撮影画像がすぐにコンピューターに表示されるため、現像作業は不要です。
代わりに、撮影画像の確認、明るさやコントラストの調整、患者情報との紐づけ、データの保存・管理といったコンピューター上での操作が主な業務となります。
まとめ
この記事では、歯科衛生士のレントゲン業務について、法律で定められた範囲と注意点を解説しました。
最も重要なのは、歯科衛生士がレントゲン撮影の照射ボタンを押す行為は法律で禁止されていることです。
- レントゲン撮影(照射行為)は法律違反であり、罰則がある
- 撮影装置の準備や調整、患者さんの誘導や位置付けの補助は可能
- レントゲン写真を読み解く「読影スキル」の習得は推奨される
ご自身の業務範囲を正しく理解し、法律を守ることが大切です。
その上で、レントゲン写真の読影スキルなどを高め、患者さんの口腔ケアに専門性を発揮していきましょう。