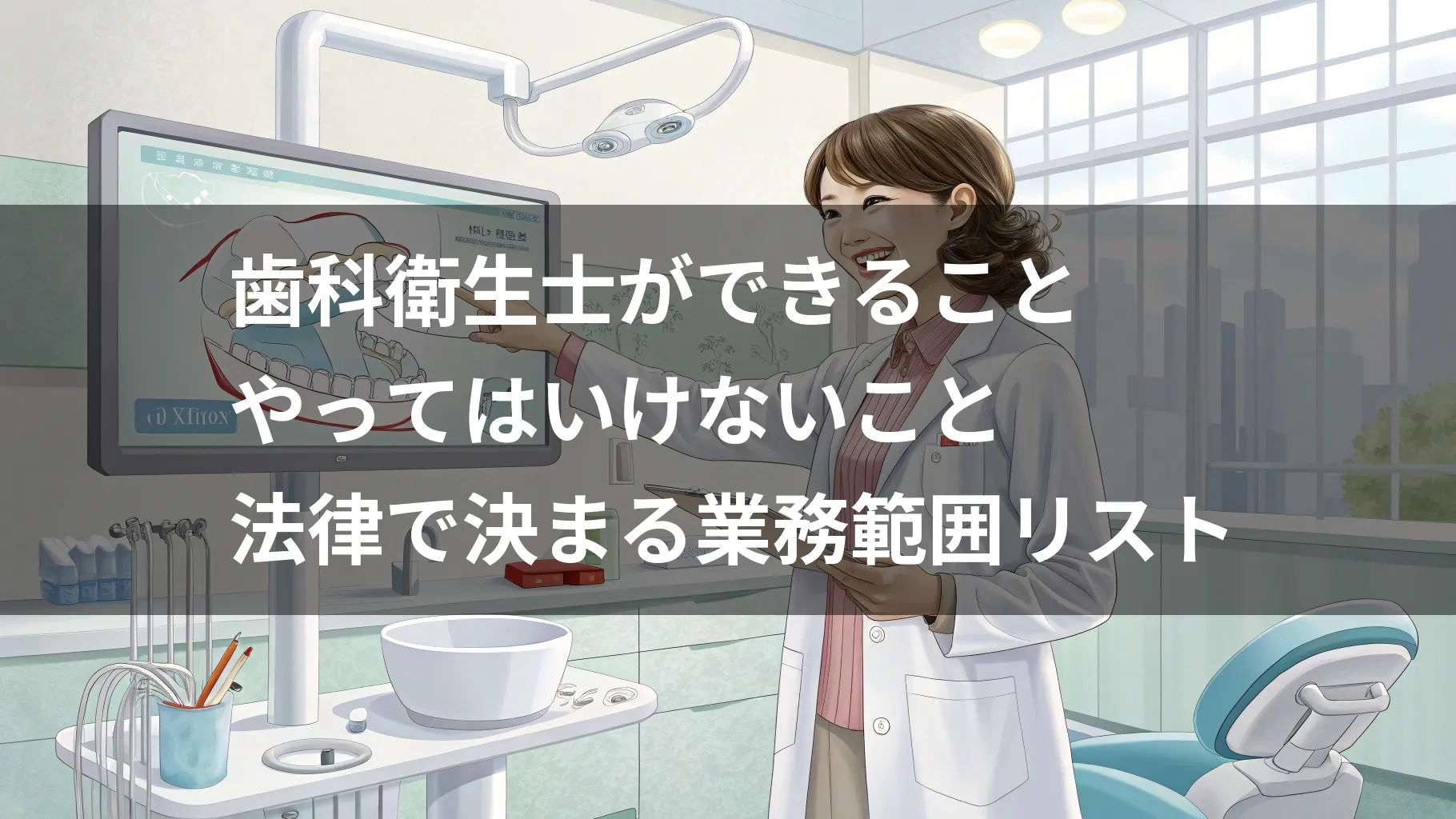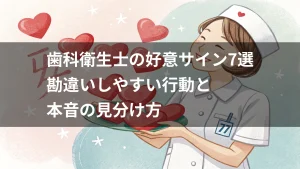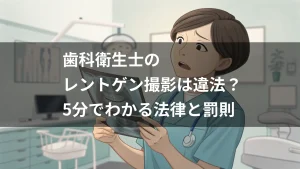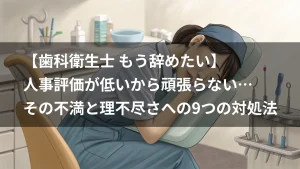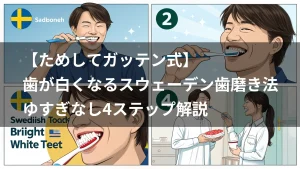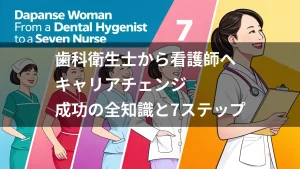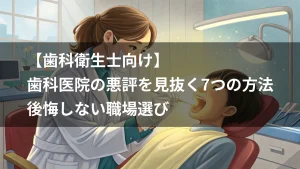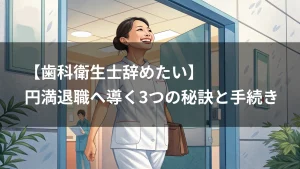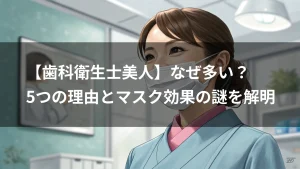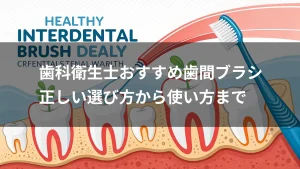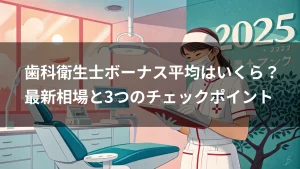歯科衛生士として働く上で、法律で定められた業務範囲を正しく理解することは、患者さんの安全と自身のキャリアを守るために不可欠です。
この記事では、歯科衛生士ができる専門的な業務(歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導など)と、法律で禁止されている行為(絶対的歯科医行為など)について、具体的な例を挙げて詳しく解説します。
 mimi
mimi日々の業務で、どこまでが自分の仕事なのか不安になる時があります…



大丈夫ですよ。この記事を読めば、できること・できないことの境界線がはっきりわかります
- 歯科衛生士が行える具体的な業務内容
- 法律で禁止されている「やってはいけないこと」のリスト
- 業務範囲を違反した場合のリスクと罰則
- 歯科助手との役割の明確な違い
歯科衛生士の業務範囲を定める法律の存在


歯科衛生士として日々患者さんと向き合う中で、自分たちに何ができて、何ができないのかを法律に基づいて正しく理解していることが、何よりも大切になります。
ここでは、私たちの業務の根幹となる歯科衛生士法、安全な医療を実現するための役割分担、そして法律を守って業務を行うことの重要性について、一緒に確認していきましょう。
法律を知ることで、自信を持って、そして安全に仕事に取り組むことができます。
歯科衛生士法とは
歯科衛生士法とは、私たち歯科衛生士の資格、仕事の内容、そして業務を行う上で守るべきルールなどを具体的に定めている法律のことです。
この法律は昭和23年に制定され、私たちの中心的な業務である「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」という3つの柱が明確に定められています。
これらの業務を通して、人々の口腔の健康を守り、向上させることが私たちの使命として記されているのです。



法律の条文って、なんだか難しそうで…



そう感じますよね。でも、大丈夫ですよ。まずは自分の仕事の範囲を定めている大切なルールだと理解することが第一歩です
歯科衛生士法は、私たちの専門職としての立場を守り、患者さんに安心して医療を受けてもらうための大切な基盤となっています。
安全な医療提供のための役割分担
歯科医療の現場では、患者さんの安全を第一に考え、それぞれの専門スタッフが明確な役割分担のもとで協力し合っています。
歯科医師は、病状の診断、治療計画の策定、そして歯を削ったり抜いたりといった治療行為そのものを担当します。
私たち歯科衛生士は、歯科医師の指示を受けて、歯石の除去やフッ素塗布といった予防処置、治療が円滑に進むための診療補助、そして歯磨き指導などの保健指導を行います。
また、歯科助手さんは、受付業務や診療器具の準備・滅菌、患者さんの誘導など、診療を縁の下で支える(ただし、患者さんのお口の中に直接手を入れることはできません)大切な役割を担っています。



チームの一員として、自分の役割をしっかり果たさないとですね



その通りです。お互いの専門性を理解し、尊重し合いながら連携することが、より良い医療につながります
このように、それぞれの職種が専門性を発揮し、責任を持って業務を行うことで、安全で質の高い歯科医療を提供することが可能になるのです。
法的根拠に基づく業務遂行の重要性
法律で定められた業務範囲をきちんと守って仕事をすることは、患者さんの安全を守ることはもちろん、私たち歯科衛生士自身を守るためにも、絶対に欠かせません。
もし、歯科衛生士法で禁止されている行為、例えば歯を削ったり、麻酔の注射をしたりといった「絶対的歯科医行為」と呼ばれる行為を行ってしまうと、法律違反となります。
その結果、罰金や懲役といった刑事罰が科されたり、歯科衛生士免許の停止や取り消しといった行政処分を受けたりする可能性があります。
残念ながら、過去には法律違反によって歯科医師と歯科衛生士が逮捕されてしまった事例も実際にあります。



もし、医院の方針でグレーゾーンなことを頼まれたら不安です…



その気持ち、よく分かります。もし業務範囲について少しでも疑問や不安を感じたら、決して曖昧にせず、勇気を持って歯科医師に確認したり、場合によってははっきりと断ったりすることが、自分を守るために重要ですよ
常に法律を意識し、定められた範囲内で責任感を持って業務に取り組む姿勢こそが、患者さんからの信頼を得て、プロフェッショナルとして輝くための礎となります。
歯科衛生士に認められた専門業務


歯科衛生士は、患者さんのお口の健康を守るために、多岐にわたる専門的な業務を行います。
その中でも特に中心となるのが、「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」という「三大業務」です。
これらの基本業務に加えて、近年ではホワイトニングに関する施術やアドバイス、口腔機能訓練といった分野でも、歯科衛生士の専門性が求められています。
これらの業務は、歯科医師との連携のもと、法律で認められた範囲内で行われます。
患者さんの口腔状態やニーズに合わせて、これらの業務を適切に組み合わせ、健康維持・増進に貢献することが、歯科衛生士の大切な役割といえます。
歯科予防処置の具体的内容
歯科予防処置は、虫歯や歯周病といったお口の二大疾患を未然に防ぐための、歯科衛生士にとって非常に重要な業務です。
これらは歯科医師と歯科衛生士のみが行える専門的な処置であり、歯科助手は行うことができません。
具体的には、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)や歯石、着色汚れなどを専用の器具や機械を使って除去します。
歯石の除去(スケーリング)は、歯肉の健康を守る上で欠かせません。
歯周ポケット内の歯石除去(SRP:スケーリング・ルートプレーニング)も歯科医師の指示のもと行います。
| 処置の種類 | 内容 |
|---|---|
| スケーリング | 歯肉縁上・縁下の歯石除去 |
| PMTC | 専用機械による歯面清掃、バイオフィルム除去 |
| フッ化物歯面塗布 | 歯質強化、虫歯予防のためのフッ素塗布 |
| 小窩裂溝填塞(シーラント) | 奥歯の溝を樹脂で埋め、虫歯を予防 |



歯石取りって、どれくらいの頻度でするのがいいんだろう?



歯石の付きやすさは個人差が大きいですが、一般的には3ヶ月〜半年に1度の定期的なクリーニングをおすすめしています
これらの予防処置を定期的に受けていただくことで、お口のトラブルを効果的に防ぎ、生涯にわたってご自身の歯で食事ができる可能性を高めます。
歯科診療補助の具体的内容
歯科診療補助は、歯科医師が行う治療が安全かつスムーズに進むようにサポートする業務です。
歯科医師の指示のもと、連携を取りながら進めていくことが求められます。
治療に使用する器具の準備や受け渡し、患者さんの唾液や水を吸い取るバキューム操作といった基本的なアシスタント業務に加え、歯科医師の指示・監督下で行える「相対的歯科医行為」も含まれます。
治療内容によって歯科衛生士が補助する範囲は異なりますが、患者さんへの声かけや状態の確認なども大切な役割です。
| 補助業務の例 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 治療器具の準備・滅菌 | 治療に必要な器具の準備、洗浄、滅菌、管理 |
| 印象採得(概形印象) | 研究用模型や対合歯列模型のための歯型採り |
| バキューム操作 | 治療中の唾液や水の吸引 |
| 仮歯(テック)の調整・仮着 | 歯科医師の指示に基づく仮歯の調整や一時的な装着 |
| セメント除去 | 詰め物や被せ物を装着した後のはみ出したセメント除去 |
| 抜糸 | 治療後の縫合糸の除去 |
| インプラント治療補助 | 器具の準備、手術中のアシスタント業務 |
| 矯正治療補助 | 装置の準備、口腔内写真撮影、ブラッシング指導 |



先生の指示があれば、どこまで手伝っていいのか迷う時があるな…



歯科医師の明確な指示と監督があれば行える業務も多いです。不安な時は必ず確認しましょう
歯科医師が治療に専念できるよう、先を読んで行動し、円滑なチーム医療を支えることが歯科診療補助の重要なポイントです。
歯科保健指導の内容
歯科保健指導は、患者さん一人ひとりがご自身の口腔ケアを適切に行えるように、専門的な知識や技術を伝え、サポートする業務です。
虫歯や歯周病は生活習慣と深く関わっているため、セルフケア能力の向上が予防の鍵となります。
指導の中心となるのは、TBI(Tooth Brushing Instruction)とも呼ばれる歯磨き指導です。
患者さんのお口の状態や歯並び、ライフスタイルに合わせて、適切な歯ブラシの選び方、動かし方、歯磨き粉の選択、デンタルフロスや歯間ブラシといった補助清掃用具の必要性や使い方などを具体的にお伝えします。
| 指導内容の例 | 具体的なアプローチ |
|---|---|
| 歯磨き指導(TBI) | 染め出しによる磨き残しチェック、個々に合った磨き方指導 |
| 食生活指導 | 間食のタイミングや回数、糖分の摂取に関するアドバイス |
| フッ化物の利用指導 | 家庭でできるフッ化物配合歯磨剤の効果的な使い方など |
| 禁煙指導 | 喫煙が口腔内に及ぼす悪影響の説明と禁煙サポート |
| 集団指導 | 学校や地域での歯磨き教室、講演会の実施 |



患者さんにうまく伝えられているか、いつも不安になる…



一人ひとりの生活習慣に合わせて、具体的で実践しやすいアドバイスを心がけることが大切ですよ
歯科保健指導は、小さなお子さんからご高齢の方まで、あらゆる年齢層の方々が対象となります。
専門的な知識をわかりやすく伝え、患者さんのモチベーションを高め、行動変容を促すコミュニケーション能力が求められます。
ホワイトニング施術とそのアドバイス
ホワイトニングは、歯の着色汚れを分解し、歯本来の白さを取り戻したり、より白くしたりするための施術です。
歯科衛生士は、歯科医師の指示のもと、このホワイトニング施術を行うことができます。
歯科医院で行う「オフィスホワイトニング」では、歯科衛生士が患者さんの歯の表面に専用の薬剤を塗布し、特殊な光を照射して歯を白くしていきます。
また、ご自宅で行う「ホームホワイトニング」の場合には、患者さん専用のマウスピースを作成し、使用方法や注意点などを詳しく説明します。
施術後の食事制限や、白さを長持ちさせるためのメンテナンス方法、知覚過敏が出た場合の対処法など、アフターケアに関するアドバイスも重要な業務です。
| ホワイトニング関連業務 | 内容 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング施術 | 薬剤塗布、光照射、術中・術後の管理 |
| ホームホワイトニング指導 | マウスピースの使用方法、薬剤管理、注意事項の説明 |
| カウンセリング | 患者さんの希望のヒアリング、施術方法の説明、リスク説明 |
| アフターケア指導 | 食事制限、メンテナンス方法、知覚過敏対策などの説明 |



ホワイトニングって、しみたりしないかな?



薬剤の種類や濃度によって、一時的に知覚過敏が出ることがあります。事前にしっかり説明し、必要に応じて対策を行います
歯の審美性への関心が高まる中で、ホワイトニングは人気の高い施術の一つです。
日本歯科審美学会が認定する「ホワイトニングコーディネーター」という資格もあり、専門性を高めることができます。
口腔機能訓練の実施
口腔機能訓練は、加齢や病気などによって低下した「食べる」「話す」「呼吸する」といったお口周りの機能を維持・向上させるためのリハビリテーションです。
特に高齢化が進む現代において、その重要性はますます高まっています。
歯科衛生士は、歯科医師や他の医療専門職と連携しながら、咀嚼(噛む力)や嚥下(飲み込む力)に問題を抱える患者さんに対して、口腔機能訓練を実施します。
舌や唇、頬の筋肉を鍛えるエクササイズ、唾液の分泌を促すマッサージ、安全に飲み込むための嚥下体操などが具体的な訓練内容です。
| 口腔機能訓練の例 | 目的 |
|---|---|
| 舌・口唇・頬の体操 | 食べる・話すための筋力向上 |
| 唾液腺マッサージ | 唾液分泌促進、口腔乾燥の緩和 |
| 嚥下体操 | 安全な飲み込みのサポート、誤嚥予防 |
| 発声・構音訓練 | 明瞭な発音の維持・改善 |
| 食事介助に関する助言 | 安全で楽しい食事のための環境調整や姿勢のアドバイス |



食べるのが大変そうな患者さんに、何かできることはないかな?



口腔機能訓練は、患者さんの「食べる楽しみ」を取り戻すお手伝いができます。多職種連携も大切になりますね
口腔機能の維持・向上は、誤嚥性肺炎の予防や栄養状態の改善、コミュニケーションの維持にも繋がり、患者さんの全身の健康と生活の質(QOL)の向上に大きく貢献します。
歯科衛生士が行えない禁止業務


歯科衛生士として働く上で、絶対にやってはいけない業務があることを知っておくのは、自分自身と患者さんを守るために非常に大切です。
これらの禁止業務は、法律で厳しく定められており、大きく絶対的歯科医行為と、注意が必要なレントゲン撮影や麻酔注射の扱い、そして歯科医師の指示・監督下でのみ行える相対的歯科医行為に分けられます。
業務範囲を正しく理解し、日々の臨床に臨むことが求められます。
絶対的歯科医行為に該当する治療
絶対的歯科医行為とは、法律によって歯科医師にしか行うことが認められていない医療行為のことです。
これらは高度な医学的判断と技術を必要とするため、歯科衛生士が行うことは厳禁されています。
| 禁止されている主な治療行為 |
|---|
| 歯を削る |
| 歯を抜く(抜歯) |
| 歯の神経を抜く(抜髄) |
| 歯茎を切る・削る・縫う |
| 詰め物や被せ物を最終的に装着する |
| 噛み合わせを取る(咬合採得) |
| 精密な歯型を取る(精密印象採得) |



もし間違ってやってしまったら、どうなるの?



法律違反となり、罰則を受ける可能性があります
これらの行為は、患者さんの安全に直結するため、決して行ってはいけません。
レントゲン撮影と麻酔注射の扱い
歯科診療に欠かせないレントゲン撮影と麻酔注射ですが、これらの操作も歯科衛生士が行えない行為に含まれます。
特にレントゲン撮影については、準備や患者さんの誘導などの補助は可能ですが、実際にX線照射のボタンを押す行為は、歯科医師または診療放射線技師しか行えません。
| 行為の種類 | 歯科衛生士の可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| レントゲン撮影 | ×(操作不可) | 診療放射線技師法 |
| 麻酔注射 | × | 歯科医師法、絶対的歯科医行為 |
| 表面麻酔の塗布 | ◯(指示・監督下) | 相対的歯科医行為 |
注射針を用いた麻酔も同様に禁止されています。
歯科衛生士が行えるのは薬剤を歯茎の表面に塗るタイプの表面麻酔のみで、これも歯科医師の指示・監督が必要です。
歯科医師の指示・監督下で行える相対的歯科医行為
一方で、相対的歯科医行為と呼ばれる、歯科医師の具体的な指示と監督があれば、歯科衛生士が行うことのできる業務もあります。
これらは歯科衛生士の専門性を活かせる業務が多く、スキルアップとともに任される範囲が広がることもあります。
| 主な相対的歯科医行為 | 留意点 |
|---|---|
| 歯石除去(スケーリング) | 歯肉縁上の歯石除去は予防処置に含まれる |
| 歯周ポケット内の歯石除去 | 歯科医師の診断に基づく指示が必要 |
| ホワイトニング | 薬剤塗布、光照射など |
| 表面麻酔の塗布 | 注射は不可 |
| 歯周組織検査 | 診断は歯科医師が行う |
| 仮歯の調整・仮着 | 最終的な装着は不可 |
| セメント除去・抜糸 | 治療後の処置として |



どこまでやっていいのか、判断に迷うときはどうすれば?



必ず歯科医師に確認し、自己判断で行わないことが大切です
ただし、これらの行為も歯科医師の適切な指示と監督がなければ行うことはできません。
常に安全への配慮が求められます。
歯科衛生士と歯科助手の明確な役割分担


歯科医院でチームとして働く上で、歯科衛生士と歯科助手の役割の違いを正しく理解しておくことはとても大切です。
それぞれの専門性を活かし、協力し合うことで、患者さんにより良い医療を提供できます。
ここでは、国家資格の有無や業務範囲、口の中に直接触れる処置ができるかどうか、そしてそれぞれの主な担当業務について詳しく見ていきますね。
この違いを知ることで、それぞれの専門性を尊重し、協力してスムーズな診療を進めることができます。
国家資格の有無と業務範囲
最も大きな違いは、歯科衛生士は国家資格が必要な専門職であるのに対し、歯科助手は特別な資格がなくても就けるという点です。
歯科衛生士になるためには、専門の養成機関で3年以上学び、歯科衛生士国家試験に合格する必要があります。
そのため、法律(歯科衛生士法)で定められた専門的な業務、例えば歯石除去や薬物塗布などを行うことが認められています。
一方、歯科助手は資格が必須ではないため、担当できる業務範囲は歯科衛生士よりも限定的になります。



資格がないと、できることがそんなに違うんですね…



そうなんです。だからこそ、歯科衛生士は専門職としての知識と技術が求められます
資格の有無が、それぞれの仕事内容や責任の範囲を大きく分けています。
口腔内への処置可否の違い
業務内容における決定的な違いは、患者さんの口の中に直接手を入れて処置を行えるかどうかです。
歯科衛生士は、歯科医師の指示・監督のもとで、歯石除去やフッ素塗布、歯磨き指導など、患者さんの口の中に直接触れる予防処置や診療補助を行うことができます。
しかし、歯科助手は、たとえ歯科医師の指示があったとしても、患者さんの口の中に手を入れる行為(歯石を取る、薬を塗るなど)は一切認められていません。
この「口腔内への処置可否」が、歯科衛生士と歯科助手の業務を明確に分ける最も重要なポイントとなります。
それぞれの主な担当業務
歯科衛生士と歯科助手では、担当する業務内容が異なります。
歯科衛生士は、「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」といった、専門知識と技術を要する業務が中心です。
これらは歯科衛生士の三大業務と呼ばれています。
一方、歯科助手は、診療の準備や片付け、使用した器具の滅菌・消毒、受付や会計業務、カルテの整理といった、診療を円滑に進めるためのサポート業務が主になります。
| 担当者 | 主な業務内容 | 口腔内処置 | 資格 |
|---|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 歯科予防処置(歯石除去、PMTC、フッ素塗布、シーラント)、歯科診療補助(バキューム操作、印象採得補助など)、歯科保健指導(歯磨き指導など)、ホワイトニング施術 | 可能 | 国家資格 |
| 歯科助手 | 受付・会計業務、器具の準備・片付け・滅菌消毒、診療アシスタント(口腔外からの補助)、院内清掃、カルテ管理 | 不可 | 不要 |
それぞれが自分の役割をきちんと果たすことで、連携の取れた質の高い歯科医療を提供できるのです。
歯科衛生士の業務範囲違反に伴う法的責任と罰則
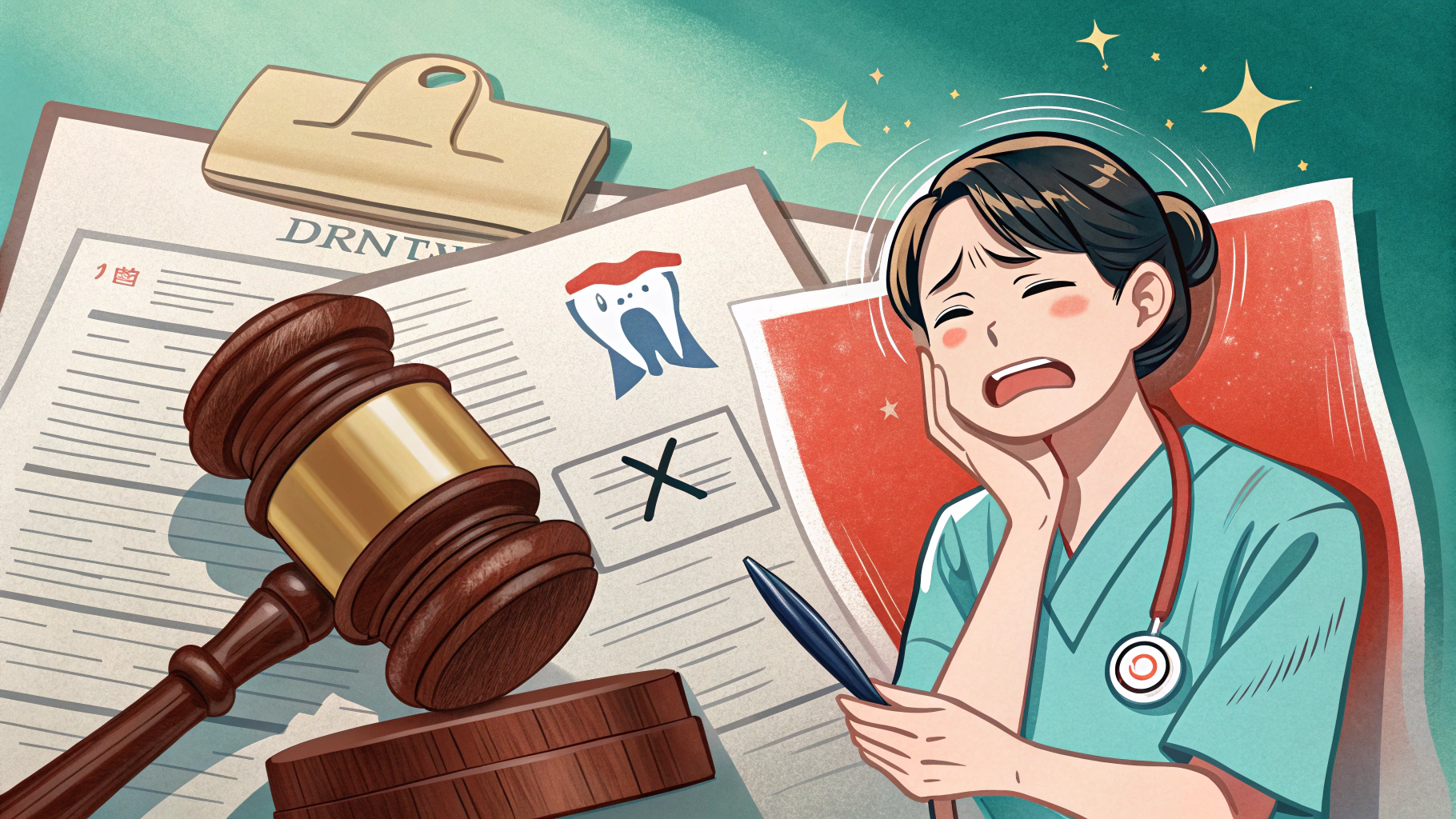
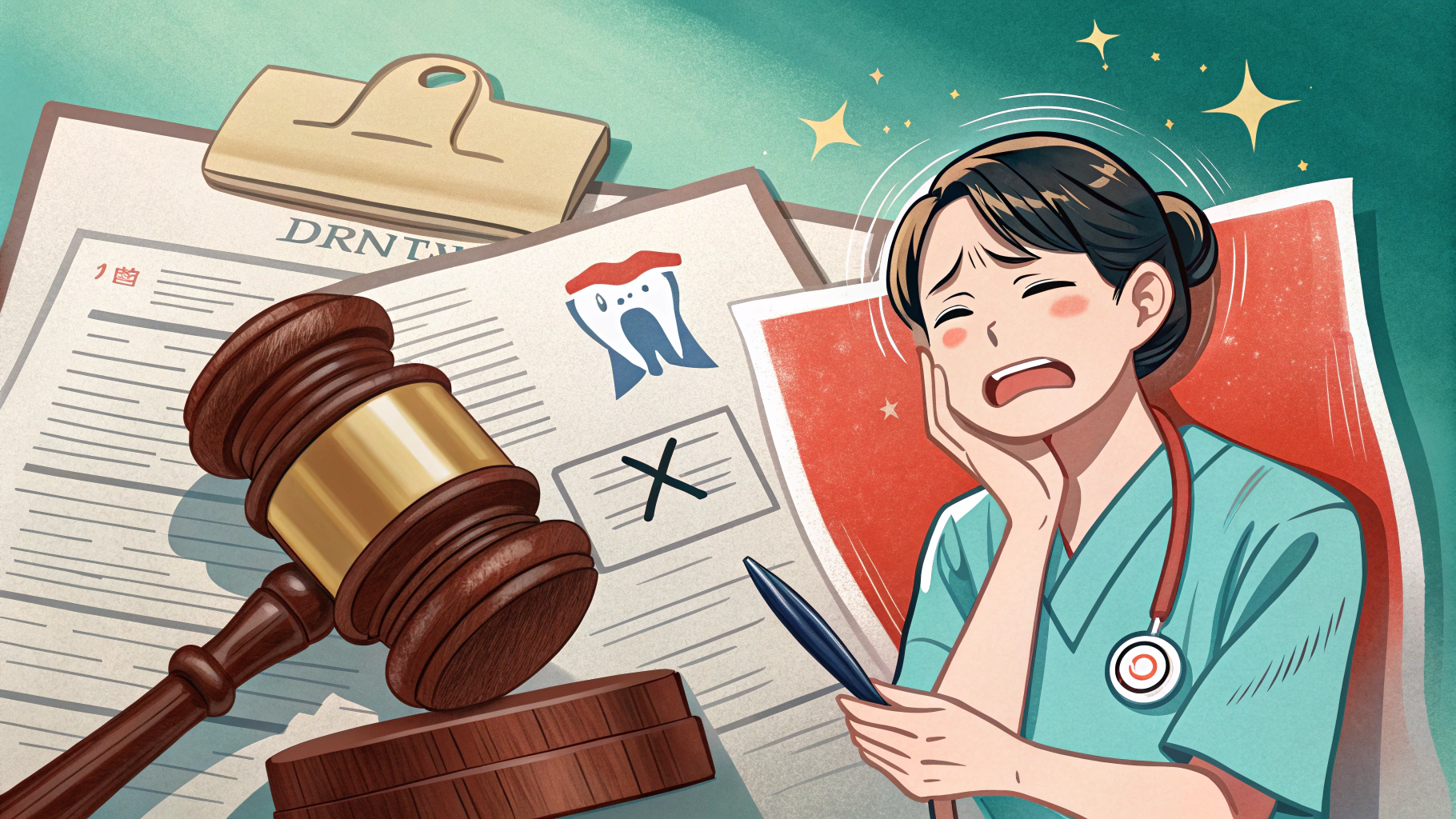
歯科衛生士として働く上で、法律で定められた業務範囲を守ることは非常に重要です。
万が一、業務範囲を超えた行為を行ってしまった場合、法的な責任を問われる可能性があります。
ここでは、どのようなケースが違反となるのか、科される可能性のある罰則、過去の事例、そして違反を防ぐための具体的な注意点について解説します。
歯科衛生士法違反となるケース
歯科衛生士の業務は歯科衛生士法によって明確に定められており、この範囲を超える行為は法律違反となります。
具体的には、歯科医師にしか認められていない絶対的歯科医行為(歯を削る、抜歯、麻酔注射、レントゲン撮影の操作など)を歯科衛生士が行うことが、最も重大な違反ケースです。
また、歯石除去やホワイトニングといった「相対的歯科医行為」であっても、歯科医師の具体的な指示や監督がない状態で行うことは認められていません。
これらの規定を遵守しない場合、歯科衛生士法違反に問われます。



どこからが違反になるのか、具体的なラインが知りたいです



歯科医師にしかできない行為をしたり、指示なく処置したりすると違反になります
自身の業務範囲を正確に理解し、歯科医師との連携を密にすることが、意図しない違反を防ぐために不可欠です。
科される可能性のある罰則内容
歯科衛生士法に違反した場合、刑事罰と行政処分の両方が科される可能性があります。
刑事罰としては、歯科衛生士法の規定(例:指示違反であれば第十五条)に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。ただし、無資格医業にあたる絶対的歯科医行為を行った場合は、歯科医師法違反としてより重い罰則が科される可能性もあります。
加えて、厚生労働大臣による行政処分として、歯科衛生士法に基づき、免許の取消し、1年以内の業務停止(第八条)、または戒告(第九条の二)といった処分が下されることもあります。
| 罰則の種類 | 内容例 | 根拠法規 |
|---|---|---|
| 刑事罰 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 歯科衛生士法 |
| 行政処分 | 戒告、業務停止(1年以内)、免許の取消し | 歯科衛生士法 |
これらの罰則は、歯科衛生士としてのキャリアに深刻な影響を及ぼすため、業務範囲の遵守は極めて重要です。
過去の事例とコンプライアンス意識
残念ながら、過去には歯科衛生士が業務範囲を超えた医療行為を行い、歯科医師と共に逮捕・起訴された事例が実際に報道されています。
例えば、歯科衛生士が患者の歯を削ったり、歯科医師の資格がない者が実質的に歯科医院を経営し、歯科衛生士に違法な指示を出していたケースなどがあります。
これらの事例は、たとえ歯科医師からの指示があったとしても、法律で禁止されている行為を行えば処罰の対象となることを示しています。
コンプライアンス(法令遵守)意識を常に高く持ち、業務にあたることが求められます。



実際に逮捕されたりするんですね…知らなかったです



はい、軽い気持ちで行うと重大な結果につながる可能性があります
過去の事例から学び、日々の業務において「これは本当に自分の業務範囲内か?」と自問する姿勢が大切です。
違反を防ぐための日々の注意点
業務範囲違反は、知らなかった、うっかりしていた、という言い訳が通用しません。
意図しない違反を防ぐためには、日々の具体的な注意が不可欠です。
自身の業務範囲を正確に把握することはもちろん、少しでも疑問に思う指示や、グレーゾーンだと感じる業務については、安易に引き受けずに必ず歯科医師に確認しましょう。
また、できないことや法的に問題のある指示に対しては、勇気を持って断る姿勢も必要です。
日頃から歯科医師や他のスタッフと良好なコミュニケーションを取り、互いの役割と責任範囲について共通認識を持っておくことも、違反を未然に防ぐ助けとなります。
| 注意点 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 業務範囲の正確な把握 | 歯科衛生士法の関連条文や厚生労働省の通知、関連ガイドラインを確認する |
| 曖昧な指示の確認 | 少しでも疑問があれば、処置を行う前に必ず歯科医師に口頭や書面で確認する |
| 歯科医師とのコミュニケーション | 日頃から報告・連絡・相談を徹底し、業務範囲に関する認識のずれを防ぐ |
| できないこと・不明なことは断る | 自身の知識や技術を超える指示、法的に問題がある指示は明確に断る |
| 最新情報の確認 | 学会や研修会への参加、専門誌の購読などで常に知識をアップデートする |
これらの注意点を日々意識し、実践することが、あなた自身と患者さんを守ることに繋がります。
よくある質問(FAQ)
歯科医師からの指示が曖昧な場合、どうすれば良いですか?
歯科医師からの指示内容が、ご自身の歯科衛生士としての業務範囲を超えていると感じたり、具体的な内容がよくわからなかったりする場合は、決して自己判断で業務を行わないでください。
患者さんの安全を守るため、そしてご自身の法的立場を守るためにも、処置を始める前にもう一度、歯科医師に直接確認することが重要です。
業務範囲や指示内容について、日頃から歯科医師と明確なコミュニケーションを取ることを心がけましょう。
歯科衛生士として経験を積むと、できる業務は増えますか?
はい、経験やスキルが向上することで、任される業務範囲が広がることはあります。
特に、歯科医師の指示・監督のもとで行うことができる「相対的歯科医行為」と呼ばれる業務、例えば歯周ポケット内の歯石除去(SRP)や仮歯の調整・仮着などは、習熟度に応じて任されるようになる場合があります。
ただし、どのような経験を積んでも、歯を削るなどの「絶対的歯科医行為」は法律で禁止されており、歯科衛生士ができることには明確な限界があることを忘れないでください。
表面麻酔はできるのに、なぜ麻酔の注射はやってはいけないのですか?
歯科衛生士が行えるのは、歯茎の表面に薬剤を塗る「表面麻酔」のみであり、これも歯科医師の指示・監督下で行う必要があります。
注射針を用いた麻酔は、血管や神経を損傷するリスクが伴い、全身的な影響を及ぼす可能性もある高度な医療行為です。
そのため、法律で歯科医師のみが行えると定められている「絶対的歯科医行為」にあたり、歯科衛生士が行うことは厳しく禁止されています。
スケーリングやPMTCは、歯科衛生士だけで判断して進めても良いのでしょうか?
歯石除去(スケーリング)や歯面のクリーニング(PMTC)は、歯科衛生士の中心的な業務である歯科予防処置に含まれます。
しかし、これらを行う前には、必ず歯科医師による診察と診断が必要です。
特に歯周ポケット内の歯石除去(SRP)などは、歯周病の状態を正確に把握した上での歯科医師の指示に基づいて行わなければなりません。
歯科衛生士が独自に診断し、治療計画を立てて処置を進めることはできません。
忙しい医院だと、ついやってはいけないことを頼まれそうで不安です。
もし、明らかに歯科衛生士の業務範囲を超える行為や、法律に抵触する可能性のある行為(例えばレントゲン撮影のボタンを押すなど)を指示された場合は、患者さんの安全とご自身の身を守るために、勇気を持って断ることが必要です。
知らないうちに違法行為に加担してしまうと、厳しい罰則を受ける可能性があります。
業務範囲に関する疑問や不安は放置せず、必ず確認し、適切な対応をとってください。
歯科助手さんに、どこまで業務をお願いして良いか迷うことがあります。
歯科助手さんは、患者さんのお口の中に直接手を入れる医療行為は一切できません。
器具の準備や片付け、滅菌、受付業務、診療中のバキューム操作(口腔外からの補助)などを担当してもらいます。
歯科衛生士が行うべき専門的な業務、例えば歯石除去や印象採得、歯面への薬剤塗布などを歯科助手さんにお願いすることはできません。
チームとして円滑に連携するためにも、それぞれの役割と業務範囲を正しく理解し、尊重し合うことが大切です。
まとめ
この記事では、私たち歯科衛生士の業務範囲について、法律で定められた「できること」と「やってはいけないこと」を具体的に解説しました。
患者さんの安全を守り、私たち自身のキャリアを築いていく上で、業務範囲の正しい理解は非常に重要になります。
- 歯科衛生士に認められた専門業務(歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導など)
- 法律で厳しく禁止されている絶対的歯科医行為(歯を削る・抜く・麻酔注射・レントゲン操作など)
- 業務範囲を超えた場合の法的な罰則とリスク
- 歯科助手との資格・業務内容における明確な違い
日々の業務の中で「これは自分の仕事だろうか?」と迷う場面があるかもしれません。
そのような時は、この記事の内容を参考にし、必ず歯科医師に確認する習慣を持つことが大切です。