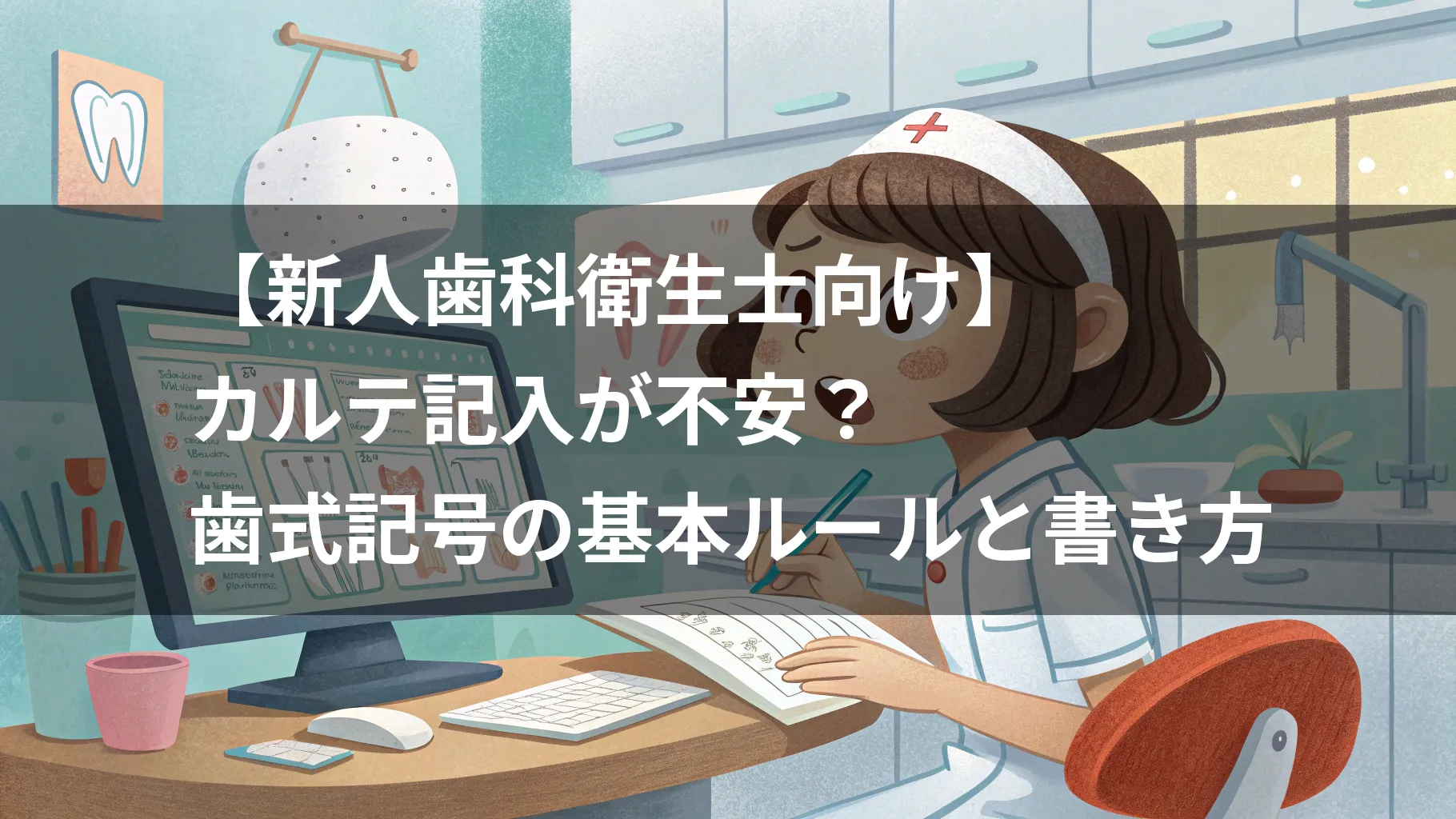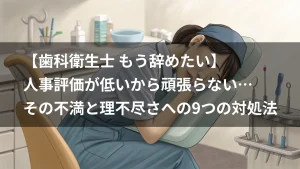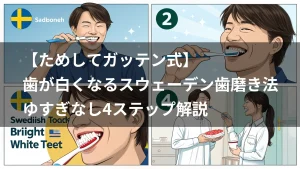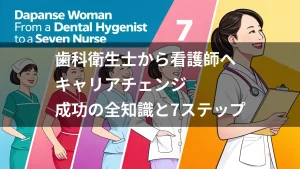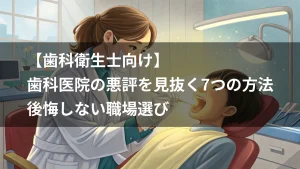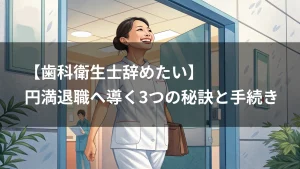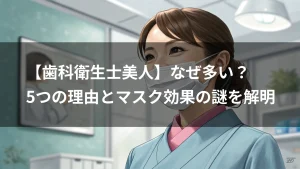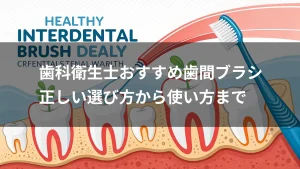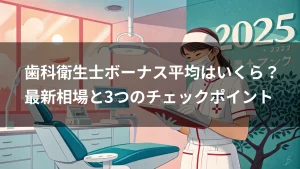歯科衛生士にとって、患者さんの情報を正確に記録するためのカルテ記入は、日々の業務における基本であり非常に重要なスキルです。
この記事では、カルテ記入の土台となる歯式記号について、日本で広く用いられるZsigmondy-Palmer方式や国際的なFDI方式といった2つの主要な表記システムの基本から、永久歯・乳歯の書き分け方、最も間違いやすい左右反転のルール、そしてC(う蝕)やP(歯周病)などの代表的な記号の意味まで、新人の方にも分かりやすく解説していきます。
 mimi
mimi歯式記号のルールや種類が多くて、ちゃんと覚えられるか不安です…



大丈夫ですよ!この記事で基本のルールとポイントを押さえれば、カルテ記入への苦手意識もきっと和らぎます。
- カルテ記入における歯式記号の重要性
- Zsigmondy-Palmer方式とFDI方式の基本ルール
- 永久歯と乳歯の歯式表記方法
- カルテ記入の左右反転ルールと代表的な記号の意味
カルテ記入の土台、歯式記号の役割


歯科医療の現場で、患者さんの情報を正確に記録し、スタッフ間で共有するために、歯式記号の理解と適切な記入は非常に重要です。
これは、日々のカルテ記入業務の土台となる知識です。
歯式記号がなぜそれほど大切なのかというと、それは歯科医師や他のスタッフとの間で情報を正確に伝達するための共通言語として機能し、さらに患者さんの大切な治療情報を正確に残し、次の担当者へ確実に引き継ぐ上で欠かせないからです。
この基本的なルールをマスターすることで、カルテ記入に対する不安が和らぎ、より自信を持って日々の業務に取り組めるようになりますよ。
チーム医療を支える共通言語の理解
歯式記号は、「どの歯について話しているか」を歯科医療チームの全員が間違いなく理解するための共通言語です。
まるで、それぞれの歯に割り当てられた住所のようなもの、と考えると分かりやすいかもしれませんね。
例えば、歯科医師から「右上6番にカリエス(むし歯)の処置をお願いします」と指示があった際、歯科衛生士は「患者さんから見て右側の上あご、中央から数えて6番目の第一大臼歯だな」と即座に、かつ正確に部位を特定できます。
このような共通の認識があるからこそ、チーム内でのスムーズな意思疎通と連携が可能になるのです。



他のスタッフと歯の話をするとき、たまに「あれ?どっちの歯のことだっけ?」って不安になることがあるんです…



大丈夫ですよ!歯式を意識して使うようにすれば、すぐに慣れて自信を持ってコミュニケーションできるようになります!
この共通言語をしっかりと身につけて使いこなすことが、指示の誤解を防ぎ、チーム全体で安全かつ質の高い歯科医療を提供することにつながっていきます。
患者情報の正確な記録と継承の重要性
カルテは、患者さん一人ひとりのお口の健康状態や治療経過を継続的に記録する、法的な意味合いも持つ重要な文書です。
歯式記号を使って、「C2」(象牙質まで達したむし歯)や「P3」(中等度の歯周病が認められる状態)といった具体的な口腔内の状態を正確に記録しておくことで、次回の診療時や、万が一担当者が変わった場合でも、過去の状況を誰でも正確に把握でき、それに基づいた適切な治療計画の立案や継続的なケアにつなげることができます。
また、保険請求(レセプト)を行う際にも、このカルテ記録の正確性が求められます。



前の担当の衛生士さんのカルテを見て、「これってどういう意味だろう?」って悩むこともあります…



誰が見ても正確に伝わるように、ルールに則って記録を残すことが、患者さんのためにも、私たち自身のためにも大切ですね。
したがって、正確な歯式を用いた記録を残すことは、患者さんの大切な情報を守り、治療の継続性を保証するために不可欠であり、私たち歯科衛生士が担うべき大切な責任の一つなのです。
歯式記号の基本、2つのメジャーな表記システム
歯式記号を正確に理解し使いこなすためには、まず代表的な2つの表記システムを知ることが重要です。
日本国内で広く用いられているZsigmondy-Palmer方式と、国際的な基準であるFDI方式について、それぞれの特徴と永久歯・乳歯の表記ルールを順番に見ていきましょう。
| 表記システム | 主な使用地域 | 特徴 | 永久歯表記 | 乳歯表記 |
|---|---|---|---|---|
| Zsigmondy-Palmer方式 | 日本、アジア | 十字記号と数字/アルファベットを併用 | 数字 (1-8) | アルファベット (A-E) |
| FDI方式 | 世界各国 | 2桁の数字のみで表記 (象限番号 + 歯番号) | 数字 (1-8) | 数字 (1-5) |
これらの2つの方式を理解することで、さまざまな形式のカルテや国内外の文献に対応できるようになります。
永久歯の番号とZsigmondy-Palmer方式での記載
Zsigmondy-Palmer(ジグモンディ・パーマー)方式は、日本の多くの歯科医院で採用されている歯式表記法です。
この方式では、永久歯(親知らずを含めて最大で32本)を、お口の真ん中(正中線)から奥歯に向かって1番から8番までの数字で表します。
| 番号 | 歯の種類 |
|---|---|
| 1番 | 中切歯 |
| 2番 | 側切歯 |
| 3番 | 犬歯 |
| 4番 | 第一小臼歯 |
| 5番 | 第二小臼歯 |
| 6番 | 第一大臼歯 |
| 7番 | 第二大臼歯 |
| 8番 | 第三大臼歯(親知らず) |



十字の記号はどうやって使うんだろう?



十字の線で上下左右の場所を示し、その隅に歯の番号を書きますよ
Zsigmondy-Palmer方式は、十字の記号と数字を組み合わせることで、どの歯なのかを直感的に特定できるのが特徴です。
乳歯のアルファベットとZsigmondy-Palmer方式での記載
Zsigmondy-Palmer方式では、乳歯(全部で20本)は数字ではなく、アルファベットで表す点が永久歯との大きな違いです。
永久歯と同様に、お口の真ん中(正中線)から奥歯に向かって、AからEまでのアルファベットが順番に割り当てられています。
| アルファベット | 歯の種類 |
|---|---|
| A | 乳中切歯 |
| B | 乳側切歯 |
| C | 乳犬歯 |
| D | 第一乳臼歯 |
| E | 第二乳臼歯 |



永久歯と乳歯が混ざっている場合はどう書くの?



混在歯列期の場合、生えている歯の種類に応じて数字とアルファベットを使い分けます
永久歯を表す数字との混同を避けるために、乳歯にはアルファベットを使用すると覚えておくと良いでしょう。
国際基準FDI方式、2桁数字の読み解き方
FDI(国際歯科連盟)方式は、世界的に広く用いられている国際標準の歯式表記法で、2桁の数字のみを使って歯の位置を特定します。
この方式を理解する上で最も重要なポイントは、1桁目の数字が歯の場所(上下左右の顎の区分、すなわち象限)を示し、2桁目の数字が歯の種類を示すというルールです。
| 1桁目(象限) | 場所 | 2桁目(歯種) | 歯の種類(永久歯/乳歯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 右上顎 | 1 | 中切歯 |
| 2 | 左上顎 | 2 | 側切歯 |
| 3 | 左下顎 | 3 | 犬歯 |
| 4 | 右下顎 | 4 | 第一小臼歯 / 第一乳臼歯 |
| 5 | 右上顎(乳歯) | 5 | 第二小臼歯 / 第二乳臼歯 |
| 6 | 左上顎(乳歯) | 6 | 第一大臼歯 |
| 7 | 左下顎(乳歯) | 7 | 第二大臼歯 |
| 8 | 右下顎(乳歯) | 8 | 第三大臼歯(親知らず) |



数字だけだと、どっちの方式か混乱しそう…



FDI方式は必ず2桁で表記されるので、1桁の数字やアルファベットを使うZsigmondy-Palmer方式との違いは明確です
2桁の数字がそれぞれ何を示しているのかを正しく理解できれば、FDI方式で書かれたカルテや、国際的な論文などを読む際にもスムーズに対応できます。
FDI方式による永久歯・乳歯の具体的な表記
FDI方式では、永久歯と乳歯で、顎の区分(象限)を示す1桁目の数字が異なります。
これをしっかり区別することが大切です。
具体的には、永久歯は10番台から40番台の数字で表され、乳歯は50番台から80番台の数字で表されます。
| 対象 | 象限番号(1桁目) | 歯の番号(2桁目) | 表記範囲 | 例(右上第一大臼歯) | 例(左下乳犬歯) |
|---|---|---|---|---|---|
| 永久歯 | 1~4 | 1~8 | 11~18, 21~28, 31~38, 41~48 | 16 | – |
| 乳歯 | 5~8 | 1~5 | 51~55, 61~65, 71~75, 81~85 | – | 73 |



Zsigmondy-Palmer方式より覚えるのが難しそう…



最初は戸惑うかもしれませんが、ルールが明確なので慣れると使いやすいですよ
象限を示す番号(1桁目)と歯の種類を示す番号(2桁目)の組み合わせのルールを覚えれば、どんな歯でも2桁の数字で迷わず表記できるようになります。
実践!カルテへの歯式記入ルールと代表記号


カルテ記入の正確性は、私たち歯科衛生士の業務の根幹を支えます。
特に、歯式を扱う上で最も間違いやすく、かつ重要なのが左右の認識です。
患者さんの口腔内情報を正確に伝えるための、共通言語のルールと言えるでしょう。
ここでは、基本でありながら混乱しやすい左右反転の原則から、記入する順番や記載位置、そして日常臨床で頻繁に用いるむし歯や歯周病、欠損歯など、代表的な状態を示す記号について、具体的な書き方を一つひとつ丁寧に解説していきます。
これらのルールと記号をしっかり覚えることで、日々のカルテ記入がスムーズになり、歯科医師や他のスタッフとの情報共有も円滑に進むようになります。
最重要ルール、左右反転の原則と覚え方
カルテ記入における左右反転の原則とは、患者さんと術者(私たち歯科医療従事者)が対面して診療を行うため、術者から見た左右と患者さん自身の左右が逆になることを指します。
これは、カルテ記入において最も基本的なルールです。
つまり、患者さんの「右側の歯」に関する情報は、カルテの歯式図上では向かって左側に記入する必要があります。
例えば、患者さんの右上の第一大臼歯(右上6番)は、カルテ上では左上エリアの6番の位置に状態を書き込みます。
この方式はレントゲン写真の表示と同じで、術者が観察した見たままを直感的に記録できる利点があります。



左右を間違えそうで、いつも不安になります…



大丈夫ですよ!「患者さんの右はカルテの左」としっかり意識して、レントゲンと同じ向きで書くと覚えるとミスが減ります
この左右反転のルールは、カルテ記入の基本中の基本であり、誤りを防ぐために常に意識して記入することが求められます。
記入順序と歯のイラストへの記載位置
カルテへの記入には、情報を整理し、誰が見ても分かりやすい記録とするための決められた順序が存在します。
まず、個々の歯について記載する際は、必ず上下顎(上か下か)、左右側(右か左か)、歯種(番号やアルファベット)の順で部位を特定します。
例えば、「右上顎第一大臼歯」や「左下顎乳側切歯」のように表現します。
複数の歯にまたがる情報を記載する場合は、上顎から下顎へ、そして右側から左側の順で記録していくのが一般的です。
| 項目 | 記入ルール |
|---|---|
| 基本順序 | 上下顎 → 左右側 → 歯種 |
| 複数箇所 | 上顎から下顎へ、右側から左側の順で記載 |
| 記載位置 | 歯のイラストの外側に記号等を記入 |
う蝕の進行度を示す「C」や歯周病を示す「P」、あるいは補綴物の種類などの記号は、歯式図に描かれている歯のイラストの外側に、どの歯に対する情報か分かるように明確に記入します。
これらの順序と記載位置のルールを守ることで、後から見返したときや他のスタッフが確認する際に、迅速かつ正確に情報を把握できます。
う蝕を示す記号(C0-C4)の段階別理解
う蝕(むし歯)の状態は、その進行度に応じて「C」というアルファベット記号と数字を用いてカルテに表記されます。
これは歯科健診の結果説明などでも一般的に使われるため、患者さんにも比較的馴染みがあるかもしれません。
「C」はCaries(カリエス:むし歯)の頭文字をとったもので、C0からC4までの5段階でむし歯の深さや状態を示します。
Cの後の数字が大きくなるほど、むし歯が進行していることを意味します。
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| CO | シーオー | 初期う蝕(要観察歯、穴は開いていない状態) |
| C1 | シーワン、シーイチ | エナメル質う蝕(歯の表面に限局したむし歯) |
| C2 | シーツー、シーニ | 象牙質まで達したう蝕 |
| C3 | シースリー、シーサン | 歯髄(神経)まで達したう蝕 |
| C4 | シーフォー、シーヨン | 残根状態(歯冠部が崩壊し根だけ残った状態) |



COとC1の違いって、たまに迷います



COはエナメル質の白濁など、まだ穴が開いていない「むし歯の始まり」の状態です。適切なブラッシングやフッ素塗布で再石灰化(治癒)が期待できます。C1はエナメル質にわずかな欠損(穴)が生じた状態を指しますね
これらの各段階を正確に診断しカルテに記録することが、患者さん一人ひとりに合わせた適切な治療計画の立案や、効果的な予防指導を行う上で非常に重要となります。
歯周病を示す記号(P)と進行度の表記
歯周病に関する情報は、「P」というアルファベット記号を使ってカルテに記録するのが一般的です。
この「P」は、Periodontal disease(ペリオドンタル ディジーズ:歯周病)の頭文字から取られています。
歯周病の状態をより詳細に示すために、歯周ポケットの深さ(例:4mm以上など)や歯の動揺度、レントゲン写真で確認される歯槽骨の吸収度といった検査結果に基づいて、進行度を示す数字を「P」に付け加えて表記することもあります(例:P1, P2, P3など)。
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| P | ピー | 歯周病 |
ただし、この進行度の具体的な分類(P1、P2などをどの状態で定義するか)は、日本歯周病学会の分類基準に基づきつつも、勤務先の歯科医院によって独自のルールが設けられている場合が少なくありません。
そのため、歯周病の進行度をカルテに記入する際は、院内で統一されている表記方法を必ず確認し、それに沿って正確に記録するようにしましょう。
欠損(/)や主な補綴物(冠、ブリッジ等)の記号
歯が抜けてしまって存在しない状態(欠損)や、過去の治療によって装着された詰め物・かぶせ物(補綴物)なども、それぞれ決められた記号を用いてカルテの歯式図に分かりやすく記入します。
代表的な例として、歯が抜けている箇所には「/(斜線)」を引いて示します。
また、治療で歯全体を覆う冠(クラウン)が装着されている場合は「○(丸)」で歯のイラストを囲みます。
この際、材質によって丸の中を塗りつぶしたり(金属冠など)、白抜きのままにしたり(レジン前装冠やセラミック冠など)と区別することがあります。
失われた歯を補うブリッジの場合は、支台となる歯を「○」で囲み、欠損部の「/」を含めて連結線でつなぎます。
| 状態/治療内容 | 主な記号(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 欠損歯 | / (斜線) | 歯がない状態を示す |
| 金属冠 | ● (丸で囲み中を黒く塗る) | いわゆる「銀歯」など |
| 全部被覆冠(非金属) | ○ (丸で囲む) | 硬質レジン前装冠、CAD/CAM冠、セラミッククラウンなど |
| ブリッジ | 欠損を/とし、支台歯を連結した○で示す | 欠損歯を補う連結した補綴物 |
| インプラント | IMP、Ⓘ など (医院により異なる) | 人工歯根が埋入されている状態 |
| 義歯(部分床・総義歯) | △、( )、[ ] など (医院により異なる) | 取り外し式の入れ歯の鉤歯や範囲を示す |
| 根管治療済 | RCF、根充 など (処置内容により異なる) | 歯の根の治療が完了している状態 |
| 充填(詰め物) | インレーは形状を書き込む、CRは色を塗る等 | 比較的小さなむし歯の治療(レジン、金属インレーなど) |
これらの記号も、う蝕や歯周病の進行度と同様に、医院によって細かなルールが異なる場合があります。
例えば、使用する記号の種類や、色分け(保険診療か自費診療かなど)の有無などが考えられます。
したがって、カルテ記入を行う際は、必ず職場で定められている歯式記号のルールを確認し、それに従って正確に記録することが、誤解のない情報伝達のために不可欠です。
臨床での応用知識と注意点


日々の臨床で歯式を正確に扱うためには、患者さんから見た左右を常に意識することが何よりも重要です。
カルテ記入の基本を理解した上で、さらに臨床現場で役立つ知識や注意すべき点を押さえていきましょう。
ここでは、特に間違いやすい左右の捉え方、患者さんのお口の状態を示す無歯顎・有歯顎状態の記録、そして近年普及が進む電子カルテでの注意点について、具体的なポイントを解説します。
これらの応用知識と注意点を身につけることで、より正確でスムーズなカルテ記入が可能になり、チーム医療への貢献につながります。
患者さん基準での左右位置の確実な把握
カルテ記入において最も混同しやすいのが「左右」の考え方です。
歯科で使用する「左右」とは、常に患者さん自身の右側・左側を指します。
これは、私たちが患者さんと対面して診療を行うため、術者から見た左右と患者さんの左右が逆になるからです。
例えば、患者さんが「左上の奥歯が痛い」と訴えた場合、私たち術者から見ると右側になりますが、カルテには患者さん基準で「左上」と記録します。
具体的には、左上第一小臼歯なら「左上4番」と書くことになります。
| 基準 | カルテ記入上の「左」 | カルテ記入上の「右」 |
|---|---|---|
| 患者さん基準 | 患者さんの左側 | 患者さんの右側 |
| 術者から見た視点 | 患者さんの右側 | 患者さんの左側 |



患者さんと向き合っていると、つい自分から見た左右で考えちゃいそうになるんです…



分かります!最初は戸惑いますよね。レントゲン写真と同じ向き、と覚えると少し分かりやすいですよ
この左右のルールを徹底することが、誤った部位への処置を防ぐための基本であり、安全な医療を提供する上で不可欠です。
無歯顎・有歯顎状態のカルテへの反映
「無歯顎(むしがく)」とは、永久歯列においてすべての歯が失われた状態を指し、「有歯顎(ゆうしがく)」は1本でも歯が残っている状態を示します。
患者さんのお口の状態に合わせて、これらの用語をカルテに正確に記載します。
例えば、総義歯(総入れ歯)を使用されている方は基本的に無歯顎となりますが、インプラントやご自身の歯が1本でも残っていれば有歯顎として記録します。
| 用語 | 読み方 | 状態 |
|---|---|---|
| 無歯顎 | むしがく | すべての永久歯がない状態 |
| 有歯顎 | ゆうしがく | 1本以上の永久歯がある状態 |
これらの状態を正確に記録することは、患者さんの全体的な口腔状態を把握し、適切な治療計画や補綴計画(入れ歯やインプラントなど)を立てる上で基礎情報となります。
電子カルテ特有の入力ルールや留意事項
近年、多くの歯科医院で導入されている電子カルテシステムには、紙カルテとは異なる独自の入力ルールや操作方法が存在します。
例えば、画面上の歯式図をクリックして歯の状態(C1、Pなど)を選択したり、特定の記号や処置内容をプルダウンメニューから選んだりする操作が一般的です。
システムによっては、FDI方式での入力が基本設定となっている場合もありますので、自院の方式を確認しましょう。
- 医院独自の入力ルールやテンプレートの確認
- ショートカットキーや定型文機能の活用
- 入力ミスを防ぐためのダブルチェック体制
- ソフトウェアのバージョンアップに伴う変更点の把握
- バックアップや個人情報保護に関する規定の遵守
導入されている電子カルテの操作マニュアルを確認し、院内の入力ルールをしっかり把握することが、効率的で正確な記録のために重要です。
不明な点は、先輩スタッフやシステム担当者に早めに質問しましょう。
よくある質問(FAQ)
カルテ記入で左右を間違えないための具体的なコツはありますか?
カルテ記入の際は、常に患者さんから見た左右で考えることが基本です。
慣れないうちは、カルテと患者さんのお口を交互に見る際に、「患者さんの右側」「患者さんの左側」と心の中で確認すると良いでしょう。
また、左右対称の部位を同時に確認するなど、自分なりの確認手順を決めておくことも間違いを防ぐ助けになります。
FDI方式とZsigmondy-Palmer方式、日本の歯科医院ではどちらをよく使いますか?
日本の多くの歯科医院では、十字の記号と数字・アルファベットを組み合わせるZsigmondy-Palmer方式が一般的に使われています。
しかし、国際的な論文や学会発表、また一部の電子カルテシステムではFDI方式が採用されている場合もあるため、歯科衛生士としては両方の歯式を理解しておくことが望ましいです。
歯式記号の読み方にルールはありますか?例えば「右上6番」はどう読みますか?
はい、あります。
一般的には「部位」+「歯の種類(または番号)」で読みます。
「右上6番」の場合、「みぎうえ ろくばん」や「うじょう だいいちだいきゅうし」のように読みます。
FDI方式の「16」であれば、「いちろく」と数字で読むのが一般的です。
職場によって習慣がある場合もあるため、確認すると良いでしょう。
読み方を統一することで、スタッフ間のスムーズな情報伝達につながります。
歯がない状態を示す「/」(欠損)以外に、特殊な歯の状態を示す記号はありますか?
はい、いくつかあります。
例えば、埋伏歯(完全に骨の中に埋まっている歯)は歯のイラスト全体を丸で囲む「◯」、歯根だけが残っている状態(残根)は「C4」や「R(Rootの略)」などで示されることがあります。
これらの歯科専門用語や記号の意味は、医院によって独自のルールがある場合もあるため、職場で使用されている種類をしっかり確認することが大切です。
代表的な補綴物(クラウンやブリッジなど)は、カルテにどうやって記入するのですか?
補綴物の種類に応じて、特定の歯科 略語や記号を用いて歯式図に記入します。
例えば、クラウン(被せ物)は歯のイラスト全体を丸で囲む「◯」、ブリッジは支台となる歯とポンティック(ダミーの歯)部分を線で繋ぎ、支台歯に「◯」を記入します。
インプラントは「imp」や専用のマーク、義歯(入れ歯)の鉤歯(バネをかける歯)には「鉤」記号を使うなど、歯科カルテルールに基づいた書き方があります。
記入方法の詳細は医院によって異なる場合もありますので、確認が必要です。
歯式を効率的に練習するためにおすすめの方法を教えてください。
歯式の覚え方としては、まず基本となる永久歯と乳歯の歯番号やアルファベット、そしてZsigmondy-Palmer方式とFDI方式の対応をしっかり覚えることが第一歩です。
空の歯式図を使って、自分で様々な状態(う蝕、歯周病、欠損、補綴物など)を設定し、繰り返し記入する練習が効果的です。
実際の歯科カルテ書き方例を参考にしたり、先輩歯科衛生士や歯科助手の方にチェックしてもらったりするのも良い方法となります。
まとめ
この記事では、歯科衛生士の重要な業務であるカルテ記入、特に歯式記号の基本について解説しました。
歯式記号を正確に理解し使いこなすことは、歯科医療チーム内の円滑な情報共有と、患者さんの大切な治療情報を適切に記録・継承するために不可欠です。
- 歯科衛生士のカルテ記入における歯式記号の重要性
- 日本で一般的なZsigmondy-Palmer方式と国際的なFDI方式の特徴
- カルテ記入時の最重要ルールである左右反転の原則
- う蝕(C)、歯周病(P)、欠損(/)、補綴物(○)などの代表的な記号の意味と書き方
この記事で解説した歯式記号の基本ルールや記号の種類、書き方をしっかりと理解し、日々の業務の中で実践することで、カルテ記入への不安を減らし、自信を持って取り組んでいきましょう。